「坊主丸儲け」という言葉にあらわされるように、お寺は非課税なので儲かっており、住職の収入も高いと考えられがちです。
しかし、実際はお寺の経営は厳しく、この言葉に違和感を覚えるご住職も多いのではないでしょうか?
この記事では、お寺の経営や収入の実態、ご住職の平均年収、お寺経営の将来性などについてくわしく紹介しますので、参考にしてください。
樹木葬・永代供養墓の導入で経営の安定化を。
弊社エータイなら初期費用ゼロで建設から宣伝広告、販売、その後のフォローまで一任。
お寺の経営者の平均年収はどれくらい?
お寺の収入は非課税で法人税がかからないため、潤沢なお金があると考えられており、お寺の経営者の年収も高いと思われがちです。
しかし、規模が小さい寺院は想像以上に収入が少なく、経営難に苦しむ寺院が多くあります。
また、住職が受け取るお金は「給与」です。
サラリーマンなどの一般の給与所得者と同様、所得税や社会保険料など、さまざまな税金が収入から引かれるため、手取りは少なくなります。
「住職の年収は1,000万円以上ある」「住職は収入が高い職業である」などと思われがちですが、お寺の経営者である住職の収入はそれほど高くないというのが実態です。
特に、規模が小さい寺院の住職は、お寺の収入だけでは生活できず、兼業している人も多くなっています。
「厚生労働省『賃金構造基本統計調査(令和5年)』」によると、住職、僧侶、司祭、神主等を含む宗教家の収入は以下のようになっています。
| 年齢別 宗教家の平均年収 | 平均年収 |
|---|---|
| 平均 | 約514万円 |
| ~19歳 | 約252万円 |
| 20~24歳 | 約308万円 |
| 25~29歳 | 約322万円 |
| 30~34歳 | 約430万円 |
| 35~39歳 | 約449万円 |
| 40~44歳 | 約547万円 |
| 45~49歳 | 約555万円 |
| 50~54歳 | 約599万円 |
| 55~59歳 | 約738万円 |
| 60~64歳 | 約652万円 |
| 65~69歳 | 約505万円 |
| 70歳以上 | 約489万円 |
お寺の経営者である住職の年収は、上記を参考にすると50代後半から60代前半にかけてピークを迎えますが、それでも1,000万円には届いていません。
逆に、20代、30代の収入は約300万円から400万円ほどとなっており、比較的低い水準といえます。
ただ、これらのデータはお寺の規模や、檀家や法要の数によって大きく左右されます。お寺の経営者の収入は、お寺の規模によって大きな差があることを覚えておきましょう。
他職種との年収比較
住職、僧侶、司祭、神主等を含む宗教家の平均年収はおよそ514万円であることがわかりましたが、他の職業の人の収入と比べると、どれくらいの水準になるのでしょうか。
同じく「令和5年賃金構造基本調査」によると、主な職種の平均年収は以下のようになっています。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 管理的職業従事者 | 約885万円 |
| 研究者 | 約740万円 |
| 電気・電子・電気通信技術者 | 約748万円 |
| 金属技術者 | 約577万円 |
| 化学技術者 | 約587万円 |
| 建築技術者 | 約632万円 |
| 土木技術者 | 約604万円 |
| システムコンサルタント・設計者 | 約685万円 |
| 医師 | 約1,436万円 |
| 薬剤師 | 約578万円 |
| 法務従事者 | 約1,122万円 |
これらの数値を見ると、住職、僧侶、司祭、神主等を含む宗教家の平均年収(514万円)は、他の職種の収入に比べてかなり低いことがわかります。
514万円という年収は、僧侶や神主なども含む宗教家全体の数値ではありますが、少なくとも、「住職は儲かる」という認識と実態はかけ離れているといえるでしょう。
お寺の経営者は、お寺の収入だけで生活したり家族を養うのは難しく、何らかの仕事と兼業する人が多くなっていますが、賃金のデータからもそのような実態がわかります。
お寺の4つの収入源は?平均相場も解説
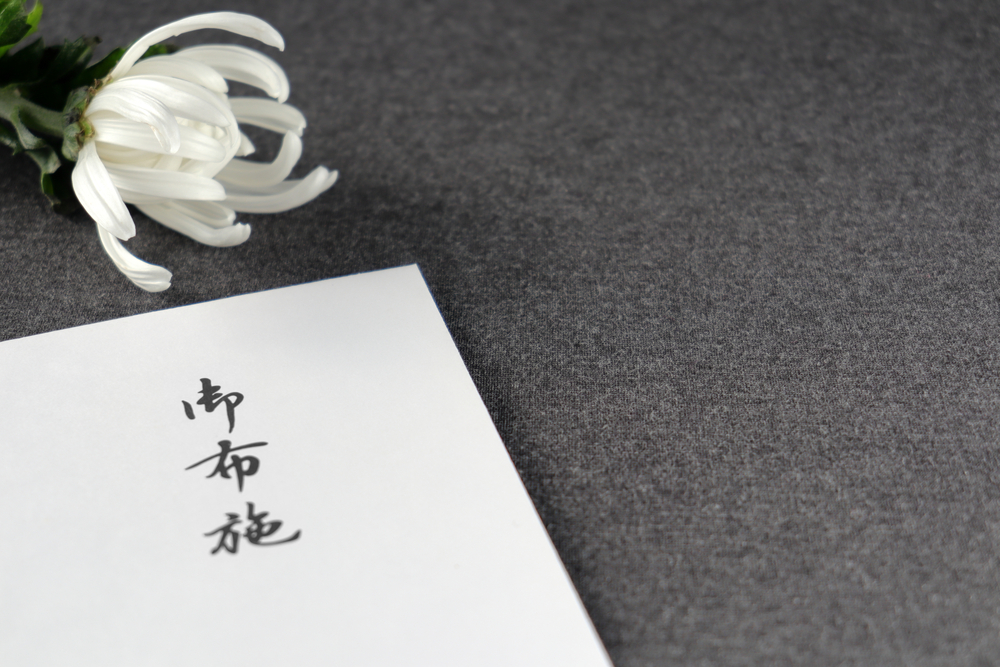
お寺経営は、主に4つの収入で支えられています。それぞれの収入源と平均相場を紹介します。
①入檀料
入檀料とは、あらたに檀家になる人がお寺に対して支払う費用で、お寺の入会金のようなものです。お寺にとっては檀家1つにつき、1回きりの収入です。
※地域・宗派により入檀料無料の寺院も増えています。
入檀料の相場は10万円~30万円ほどと言われていますが、お寺や宗旨・宗派によって大きな違いがあります。
②護持会費
護持会費とは、檀家がお寺に支払う年間の管理費です。年に1回、振込みもしくは住職に直接手渡す形で支払い、主にお寺の運営費やお墓の管理に使われます。
護持会費の平均相場は年間5,000円~2万円ほどで、お寺にとっては継続的な収入源となります。
③葬儀
葬儀で読経をした際には、お布施を受け取ります。葬儀の際のお布施の相場は、15万円~50万円となっており、お寺や宗旨・宗派、また読経の際の僧侶の数などで金額が変わります。
また、戒名を授ける場合は、別途戒名料を受け取ります。
戒名は複数のランクがありますが、最も一般的なのは「信士」や「信女」で、平均的な戒名料は以下となっています。
なお、戒名料は金額に幅があり、寺院によっては相談に応じている場合もあります。
| 宗派 | 「信士」や「信女」の平均相場 |
|---|---|
| 真言宗・天台宗 | 30万円~50万円 |
| 曹洞宗 | 30万円以上 |
| 浄土宗 | 30万円~40万円 |
| 浄土真宗 | 20万円以上 |
| 臨済宗 | 30万円~50万円 |
このように、葬儀と戒名のお布施はまとまった金額になるため、お寺の経営収入に大きく寄与しているといえます。
④法要
法要とは、亡くなった人の冥福を祈って供養する、仏教の儀式のことをいいます。
法要の種類ごとのお布施の平均相場は、以下のようになっています。
| 法要の種類 | お布施の平均相場 |
|---|---|
| 四十九日法要 | 3万円~5万円 |
| 納骨法要 | 3万円~5万円 |
| 新盆や初盆法要 | 3万円~5万円 |
| 一周忌法要 | 3万円~5万円 |
| 三回忌以降 | 1万円~5万円 |
檀家の数が多いと必然的に法要の数も増えるため、檀家が多いお寺のほうが、収入が多く経営が安定する傾向にあります。
お寺経営の収入は、前述した住職や僧侶など宗教家の年収のデータを見る限り、世の中の人が考えているよりも厳しい状態と考えられます。
お寺は、檀家によって支えられている仕組みのため、檀家が多いとお寺経営の収入が増えて安定します。
逆に檀家が減ると、経営が厳しくなる傾向があります。
一般的に、お寺の経営が安定する檀家の数は約300といわれていますが、檀家数が300を超えるお寺は多くはないとされています。
例として、それぞれの宗派が行った調査結果をみてみましょう。
寺院経営者の収入が1,000万円以上の寺院を「大規模寺院」、500万円以下を「小規模寺院」とした場合の割合は、以下のようになっています。
| 宗派 | 大規模寺院 | 小規模寺院 |
|---|---|---|
| 浄土真宗本願寺派 | 18.8% | 63.7% |
| 曹洞宗 | 17.7% | 55.1% |
| 真言宗智山派 | 20.6% | 61.1% |
この結果から、どの宗派でも、約6割の寺院が「年収500万円以下の小規模寺院であり、経営は厳しい」と考えることができます。
逆に、約2割の寺院は、年収1,000万円以上の大規模寺院です。
これらの結果から、寺院間の格差が非常に大きいことがわかります。
檀家離れも進んでいる
経営が厳しいお寺が多いことがわかりましたが、近年は「檀家離れ」と呼ばれる現象が起きており、檀家を主な収入源とするお寺にとっては、将来的にも厳しい状況が続くと考えられます。
檀家とは、お寺を支えていく人や家のことですが、お墓の承継者がいなかったり、金銭負担が重いなどの理由で、檀家を辞める人が増えています。
また、近年は永代供養墓や樹木葬など、血縁にとらわれず自分の好きなお墓を選ぶ人が増えており、一般的なお墓に入りたいという人も減っています。
このように、檀家が減っているだけでなく、新たに檀家になりたいという人も少ないという現状があります。
大規模寺院は、収入も多く、経営は安定していると考えられますが、今後も檀家離れが進んだ場合、収入が減少していくことになります。
現時点でも経営が厳しい小規模寺院においては、今後さらに檀家数の減少によって、収入が先細る懸念があるでしょう。
このように、檀家離れが進む昨今では、大規模寺院にとっても、小規模寺院にとっても、檀家だけに頼る寺院経営にはリスクがあります。
経営を安定させてお寺を末永く存続させるためには、お寺の収入源を分散化するような、何らかの取り組みが必要であるといえます。
お寺の経営の将来性について

お寺の経営収入は、今後増える見込みがあるのでしょうか。ここでは、お寺の収入を含めた将来性について、3つのデータをもとに解説します。
①法要の減少
一般社団法人「良いお寺研究会」のお寺経営者に対してのアンケートによると、「年会法要のコロナ前とコロナ後の変化」について、以下のような回答となっており、法要の回数や規模が減っていることがわかります。
- 法要の申し込みが少なく、中止や延期も多い
- 参列者の人数が少ない
- 法事後の会食が少ない
今後も法要回数の減少が続いた場合、お布施の金額も減ることから、お寺の経営収入にとってはマイナス要素といえます。
②地域の過疎化による寺院消滅のリスク
2015年に日本創生会議が発表した「消滅可能性都市」によると、2040年の段階で全国の自治体の 49.8%が消滅する可能性があるとされています。そして、それに伴って、約7万7千ほどある寺院のうち3万余りが消滅する可能性があるといわれています。
お寺を支えるのは檀家、つまり「人」であるため、過疎化が進み、地域に住む人がいなくなれば、お寺の存続は難しくなります。
このように、過疎化の問題も、お寺の経営にとってはマイナス要素といえます。
③人々の宗教観の変化
檀家制度は江戸時代から始まり、仏教が人々の生活に根付いている時代が長く続いてきました。
しかし、近年は人々の宗教観が変わってきており、無宗教の人が増えているという実態があります。
NHK放送文化研究所が参加しているISSP(International Social Survey Programme)が行った調査「日本人の宗教意識や行動がどう変わったか」によると、信仰心についての質問では、以下のような回答になっています。
| 信仰している宗教がある | 36%(仏教31%・キリスト教1%・神道1%) |
| 信仰している宗教がない | 62% |
また、信仰心がまったくないと答えた人は、18~39歳の男性では42%、女性では34 %にのぼっており、若い世代が成長する未来も、檀家が増える可能性は低いといえます。
このように、無宗教の人が増えていることも、新たな檀家を期待できない要因となっています。
ただ、無宗教の人であっても、安心して眠れるお墓は誰にでも必要です。お布施や護持会費などの需要は減っても、お墓に対するニーズは変わらないと考えられます。
お寺の経営収入を増やすためにできる取り組み

お寺の経営収入を増やして安定させるためには、檀家以外の収入源を持つことが大切です。ここでは、収入源を増やす2つの方法を紹介します。
寺院本堂を利用した葬儀を増やす
現代の葬儀は、葬儀屋で葬儀を行い、読経をする僧侶が葬儀屋に出向くのが一般的です。
しかし、お寺の収入を増やしたいのであれば、「寺院本堂を利用してもらった葬儀」を推進することもひとつの方法です。
お寺の中にご遺体が安置されることで、ご遺族もより安心できますし、葬儀の回数が増えればお布施の収入も増え、お寺の経営も安定します。
また、この「寺院葬」の費用は葬儀屋の費用よりも安いことが多いため、利用者にもメリットがあります。
「寺院葬」は格式が高いイメージがあり、仏様に近い場所で、厳かな雰囲気の中で執り行えるため、葬儀屋の葬儀と差別化できます。
ホームページやSNS、地域の集まりなどで、寺院葬を行っていることを知ってもらう取り組みを行いましょう。
永代供養墓事業を導入する
永代供養墓事業とは、寺院内に永代供養墓を建立・販売することで、新たな収入源を確保しつつ、檀家以外の人との関わりを構築することをいいます。
永代供養墓は、基本的に承継者を必要としないお墓です。独身の方や子どもに負担をかけたくないと考える方にも、安心して選んでいただけます。
寺院内に永代供養墓を建立するには、まとまった初期費用がかかると思われがちですが、エータイの永代供養墓であれば、初期費用が一切かかりません。
エータイであれば手元にまとまった資金がなくても簡単に永代供養墓を経営に取り入れられるため、金銭的な負担を負うことなく「将来のために経営改革に取り組みたい」という気持ちを実行に移すことができます。
エータイの樹木葬・永代供養墓についてくわしく知りたいという方は、ぜひ資料を取り寄せてみてください。
エータイの永代供養墓導入の流れ
エータイの永代供養墓をお寺の経営に取り入れる場合、大まかな手順は以下となっています。
- 1.打ち合わせ
- 2.ヒアリング・現地調査
- 3.プランニング
- 4.契約
- 5.許可申請
- 6.工事
- 7. 販売開始
ヒアリングでは、寺院のどの場所に、どの種類の永代供養墓を導入したいか等の希望をヒアリングします。
樹木や石などの撤去が必要な場合は、撤去についても相談します。撤去の際も、費用はかからないので安心です。
納得できるプランが出来た段階で契約を取り交わし、永代供養墓を建立します。
建立後の宣伝広告やマーケティング、見学希望者の案内、契約手続き、永代供養墓の掃除や管理まで、すべて弊社エータイが一任して行うため、寺院経営者のご負担になることはありません。
永代供養墓導入後の運営や管理もエータイが一任するため、住職の方々はこれまで通りの生活を続けることも大きなメリットとなっています。
また、万が一販売不振でなかなか売れなかったという場合でも、お寺の経営者が負債を抱えることはないので安心です。
このように、お寺の経営者がリスクを負わずに永代供養墓を導入できることが、エータイが支持される理由となっています。
エータイの樹木葬・永代供養墓についてくわしく知りたいという方は、ぜひ資料を取り寄せてみてください。
まとめ
お寺の経営収入は、お寺の規模によって大きく異なり、収入が少ない「小規模寺院」が約
6割を占めています。
住職(僧侶や神主など含む宗教家全体)の平均年収は約513万円で他の職種よりも少なく、専業で生活したり、家族を養っていくのは難しいという現状があります。
近年は「檀家離れ」が顕著になってきているため、お寺の経営を改善するには、檀家以外の収入源を持つこと、檀家以外の人との関係を築いていくことの2つが求められます。
エータイの永代供養墓は、初期費用が不要で、行政手続きから販売のマーケティング、お墓の管理まですべてエータイに一任できることが魅力です。
お寺の経営改革に取り組みたいと考えている人は、ぜひエータイの資料を取り寄せてみてください。



